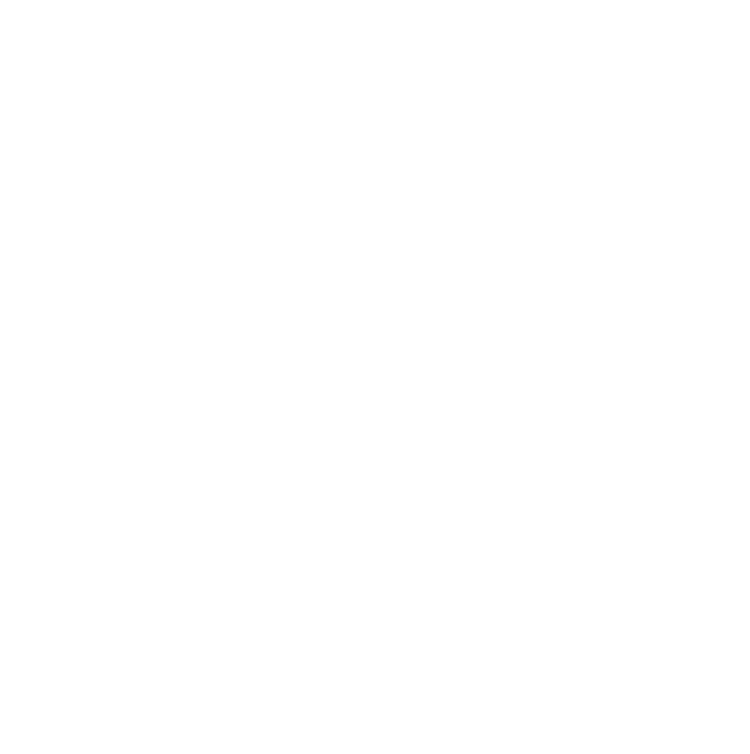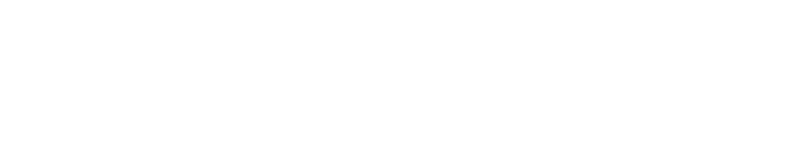■ はじめに:百日ぜきとは?
百日ぜき(正式名称:百日咳)は、ボルデテラ・パータスシス菌による呼吸器感染症です。
長期間続く激しい咳が特徴で、特に赤ちゃんや高齢者では命に関わることもあります。
ワクチン普及で一時期は減少しましたが、免疫の低下や耐性菌の出現で再び流行が起きています。
■ 百日ぜきの流行状況【最新データ紹介】
-
2024年度の百日ぜき報告数は、前年に比べて約3倍に増加。
-
鳥取県では過去の年(2018年・2019年)に比べて6倍以上の患者数(365人)を記録。
-
大阪府では**マクロライド耐性百日咳菌(MRBP)**が確認され、薬の効かない菌の広がりが懸念されています。
■ 百日ぜきの主な症状と経過
百日ぜきは、症状の進み方によって3つの時期に分かれます。
【1】カタル期(最初の2週間くらい)
-
軽い咳や鼻水、微熱など普通の風邪に似た症状から始まる。
-
徐々に咳が増えて強くなっていく。
【2】痙咳(けいがい)期(2〜3週間くらい)
-
短い咳が連続して起こる「発作的な咳」が特徴。
-
息を吸うときに「ヒュー」という音(笛声)が出る。
-
咳き込んで吐くこともあり、顔や目に出血することも。
-
特に乳児では無呼吸発作、チアノーゼ、けいれんなど重症化しやすい。
【3】回復期(2〜3週間以上)
-
発作的な咳は次第に減るが、完全に治るまでは2〜3か月かかる。
-
忘れた頃に咳がぶり返すこともある。
■ 百日ぜきの感染経路と広がり方
-
主に咳やくしゃみでうつる飛沫感染。
-
学校や保育園、家庭内で広まりやすい。
-
大人が軽症で気付かず、赤ちゃんにうつすケースも。
■ 百日ぜきの診断方法
| 検査方法 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 菌培養検査 | 鼻の奥から検体を採り、特別な培地で菌を育てる | ・確定診断ができる ・特異性が高い |
・菌を育てるのが難しい ・検査に時間がかかる ・症状が進むと検出しにくい |
| 遺伝子検査(PCR・LAMP法) | 百日ぜき菌の遺伝子を検出する | ・感度が高い ・結果が早く出る ・LAMP法は簡単で迅速 |
・症状が出て3週間以内に検査しないと正確性が下がる |
| 血清診断(抗体検査) | 血液中の抗百日咳毒素抗体(抗PT IgG)を測る | ・症状が進んでも診断できる ・簡単な採血で検査可能 |
・乳児やワクチン接種後1年以内の人には適用できない ・他の菌と区別が必要 |
■ 百日ぜきの治療
抗菌薬による治療
-
生後6か月以上:エリスロマイシン、クラリスロマイシン(マクロライド系抗菌薬)
-
新生児:アジスロマイシン(副作用予防のため)
早期に治療を始めれば、菌の排出を抑えられ、感染拡大防止にもつながります。
咳への対症療法
-
鎮咳剤(咳止め薬)
-
去痰剤(痰を出しやすくする薬)
-
気管支拡張剤(呼吸を楽にする薬)
■ 百日ぜきの予防策
ワクチン接種
-
四種混合ワクチン(DPT-IPV):ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ
-
三種混合ワクチン(DPT):ジフテリア・百日咳・破傷風(ポリオワクチン接種済みの人向け、または大人向け)
👉 乳幼児期の定期接種と、思春期や大人での追加接種が重要です。
日常生活での感染予防
-
手洗い、うがい、マスク着用
-
咳・くしゃみがあるときの外出を控える
-
体調が悪いときは無理をせず休む
■ まとめ:正しく知って、しっかり対策を
百日ぜきは、特に赤ちゃんや高齢者にとって命に関わることがある怖い病気です。
早期発見・早期治療、ワクチンによる予防、日頃の感染対策をしっかり行い、自分と周りの人を守りましょう!