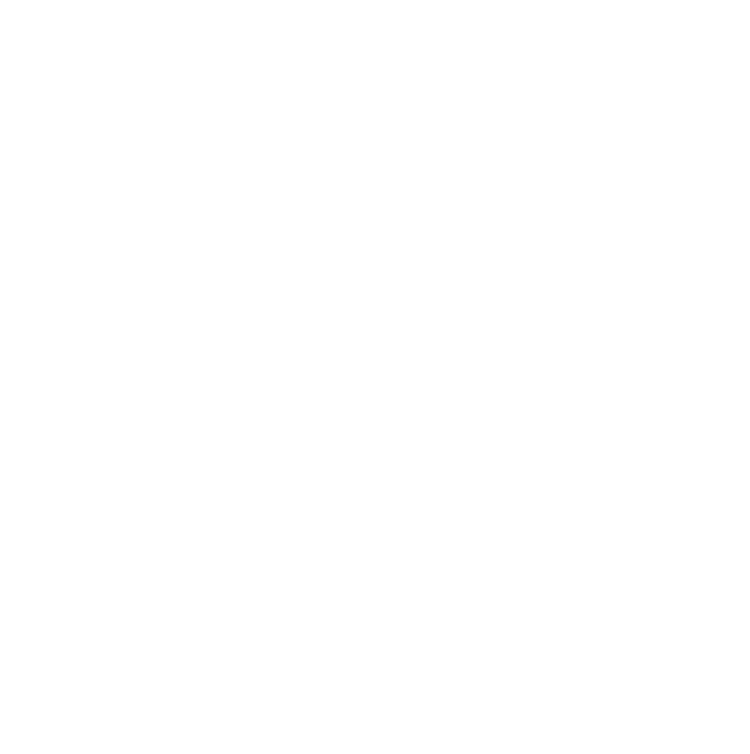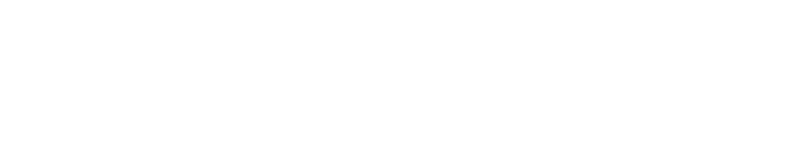鼠径ヘルニア治療では、なぜ 日帰り手術が普及しにくい のでしょうか?
答えは「病院」「患者」「保険制度」という三者の経済的利害にあります。
本記事では、国民皆保険制度の下での 医療費の流れと構造的課題 を整理し、日帰り手術普及のカギを探ります。
病院の立場:DPC制度と収益構造

入院による収益確保
病院経営では「ベッドを埋めること」が収益に直結します。
日本の DPC(診断群分類包括評価)制度 では次の特徴があります。
-
入院初日〜3日目:診療報酬が高い
-
4日目以降:報酬が段階的に減額
-
結果:4〜5日間の入院が最も収益性が高い
鼠径ヘルニア手術の場合:
-
日帰り手術:約30万円(病院収入)
-
入院手術:約50万円(病院収入)
この差額は病院にとって大きな意味を持ちます。
教育の観点
-
入院手術は 若手医師・研修医の教育機会 としても活用されやすい
-
経営+教育の両面から、病院は入院を推奨しやすい構造にあります
患者の立場:負担額と任意保険の影響
高額療養費制度で自己負担差は小さい
-
医療費は3割負担
-
高額療養費制度により上限あり
👉 30万円(日帰り)と50万円(入院)の差があっても、患者自己負担はほぼ同じ。
任意保険が与える逆インセンティブ
多くの医療保険では:
-
手術給付金:一時金が出る
-
入院給付金:1日あたり定額が出る
→ 入院した方が経済的に得になるケースもある。
患者心理
「入院した方が安心+保険でお金が出る」という心理が働き、あえて入院を選ぶ人もいる。
国の立場:医療費削減と効率化の必要性
医療費増加の現実
-
高齢化による受診者増加
-
慢性疾患患者の増加
-
医療技術の進歩による費用増
👉 財源には限界があり、効率的な医療提供が求められる。
日帰り手術の普及による効果
-
アメリカ:鼠径ヘルニアの80%が日帰り
-
日本:わずか8%
日帰り手術が普及すれば、数百億円規模の医療費削減効果 が期待できます。
三者の利害関係を比較
| 立場 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 病院 | ・入院で高収益 ・若手医師の教育機会 |
・日帰りだと収益性が低い |
| 患者 | ・高額療養費で自己負担は軽減 ・任意保険で入院が有利な場合あり |
・入院は時間的コストが大きい ・院内感染リスク |
| 国(保険制度) | ・日帰り手術普及で医療費削減 | ・現行制度では入院を優遇しており改革が遅れている |
👉 この「三者の利害不一致」が、日帰り手術普及の障壁となっています。
クリニックの取り組み:安全性と効率性の両立

例:日帰り手術専門クリニックでは
-
外科専門医による執刀
-
手術時間60分未満
-
在院時間:約4時間
-
翌日から仕事復帰も可能
-
近隣病院と連携した緊急対応
👉 患者の生活に配慮しつつ、国全体の医療費削減にも貢献しています。
これからの医療のあるべき姿
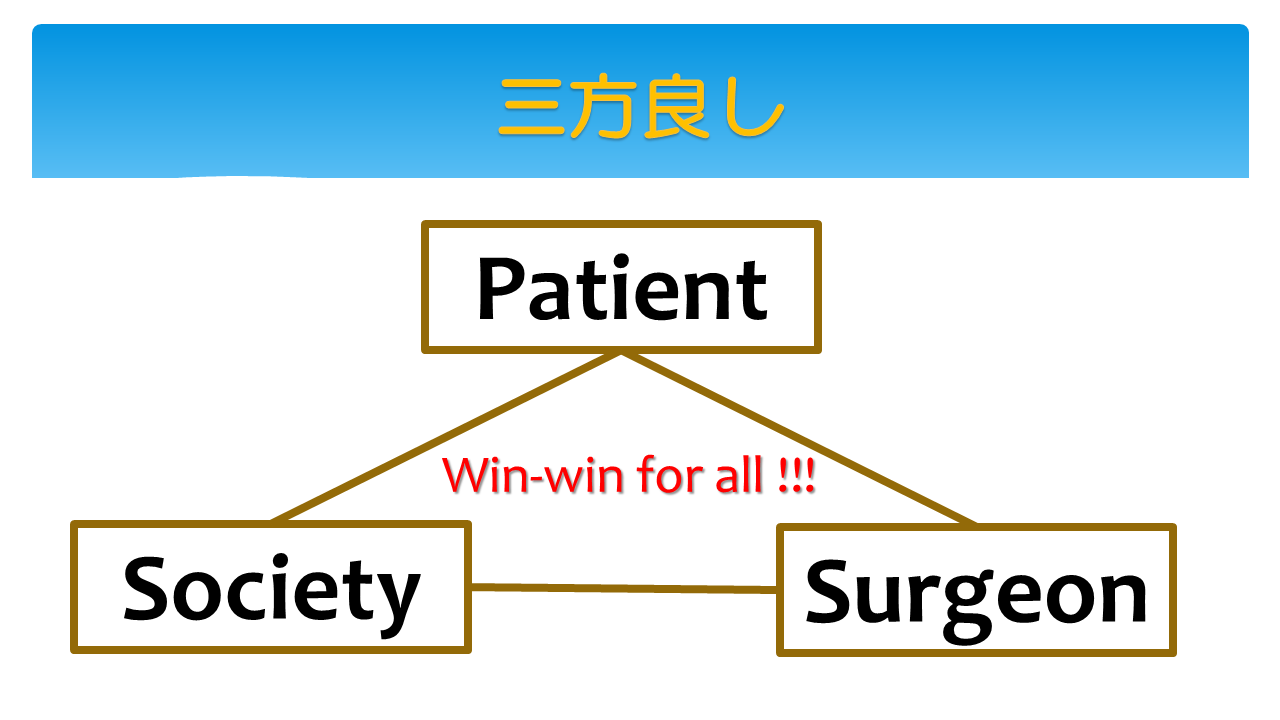
必要な変革
-
技術進歩に見合った診療報酬の見直し
-
日帰り手術を適切に評価する仕組み
-
患者負担の公平性と病院経営の安定の両立
理想の方向性
-
患者:安全で効率的な治療を受けられる
-
病院:適正な収益と教育機会を確保できる
-
国:持続可能な医療財政を維持できる
よくある質問(FAQ)
Q1. 任意保険に入っていると入院の方が得ですか?
A. 保険の内容によります。入院給付金がある場合はプラスになることもあります。
Q2. 日帰り手術と入院手術で質に差はありますか?
A. 適切な患者選択と技術があれば差はありません。むしろ感染リスクは日帰りの方が低いです。
Q3. なぜ病院は入院を勧めるのですか?
A. 現行制度では入院の方が収益性が高いため。また教育目的の側面もあります。
Q4. 医療費削減は患者に不利益をもたらしませんか?
A. 適切な制度改革により、効率化と患者利益は両立可能です。
まとめ
-
病院は収益・教育のため入院を推奨
-
患者は自己負担が少なく、保険給付で入院が有利になる場合も
-
国は財政的に日帰り手術を推進したい
この三者の利害が噛み合わないことが、日帰り手術普及の最大の障壁です。
👉 制度改革により「患者利益」「病院経営」「国の財政」の三方よしを実現することが、これからの医療に求められています。