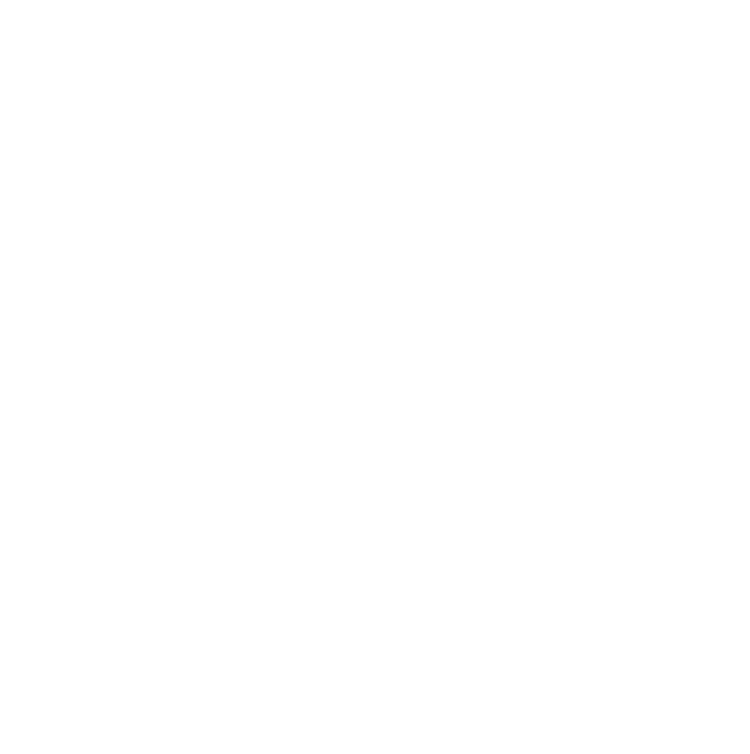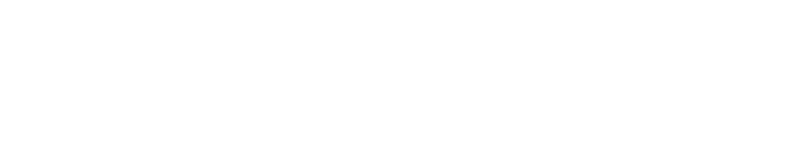こんにちは、外科医の太田です。
本日は少し難しいテーマではありますが、「再生医療」と、それに関わる「研究不正・捏造」について、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。
ドラマが描いた“再生医療”と研究不正
最近放送されていたドラマ『キャスター』の中で、第3話に「再生医療」とそれに関わる「論文の不正や捏造」がテーマとなっている回がありました。これは決してフィクションにとどまらず、私たち医療現場でも実際に問題視されている重要なテーマです。
病気は6つのカテゴリーに分けられる
医師の立場から見ると、病気は大きく6つのカテゴリーに分類されます:
-
炎症(例:風邪、免疫疾患など)
-
循環(例:脳梗塞、心筋梗塞など)
-
腫瘍(例:がんなど)
-
欠損(器官や組織が失われた状態)
-
変性(組織の質が劣化する病気)
-
代謝(体内での化学反応がうまくいかない病気)
中でも後半の「欠損」「変性」「代謝」に関連する病気は、命を脅かすだけでなく、日常生活の質を大きく低下させる厄介なものです。
こうした疾患の例:
-
視力を失った方
-
下半身不随の方
-
生まれつき糖尿病で腎臓が壊れてしまい、人工透析が必要な方
-
心臓の機能が低下し、かつて楽しんでいた山登りもできなくなった方
このような方々を、私たちと同じレベルの生活に近づけるにはどうすればいいのか――
そこで登場するのが「再生医療」です。
再生医療とは何か?
再生医療とは、「壊れた身体を再びよみがえらせる」あるいは「失われた機能を新たに作り出す」ことで、健康な状態に近づけようとする医療分野です。
従来の治療(薬や手術)では根本的に治せなかった病気に対して、再生医療はまったく新しいアプローチを提供します。
再生医療の適応例:
-
目の疾患
-
脳・脊髄(パーキンソン病など)
-
心臓
-
膵臓(糖尿病など)
特にこれらの臓器では、従来の医療技術では回復が難しかった部分に対して、新たな希望をもたらしています。
再生医療の鍵「多能性幹細胞」とは?
再生医療で注目されているのが、「多能性幹細胞」と呼ばれる細胞です。
かつての課題と倫理的議論
初期の研究では「受精卵」を使用していたため、倫理的な問題から研究の進展が難航しました。
そして登場した「iPS細胞」
このような背景の中、2006年に山中伸弥教授によって発見されたのが「iPS細胞(人工多能性幹細胞)」です。
iPS細胞の登場により、倫理的な問題を回避しながら、さまざまな細胞に分化できる画期的な技術として再生医療が一気に進展しました。
現在(2025年5月時点)、すでに**目や脳(パーキンソン病)**の治療にiPS細胞が使われ始めており、他の臓器への応用も続々と進んでいます。
現在の公的認可と未来
現時点では、厚生労働省が先進医療として認可しているのは「目の病気へのiPS細胞応用」ですが、これも税金補助を受けて進行中の正式な治療です。
iPS細胞の発見により、再生医療はまさに「医療の革命」とも言える飛躍を遂げています。
この功績により、山中教授は2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。
再生医療にも課題はある
とはいえ、iPS細胞にもまだまだ課題は残されています。
この点については、次回の動画(または記事)で詳しくご紹介します。
この記事は外科医・太田勝也が解説しました。
再生医療の最新動向について、今後もわかりやすく発信していきます。
チャンネル登録・フォローよろしくお願いします!